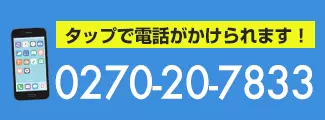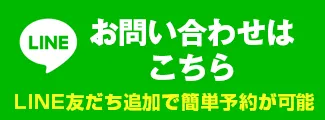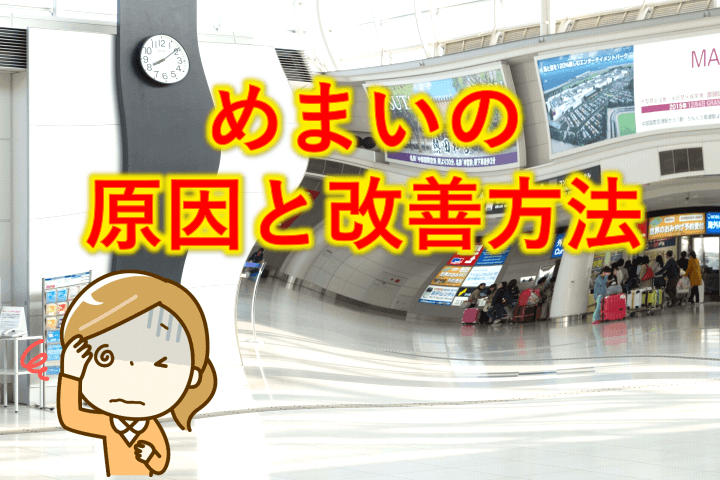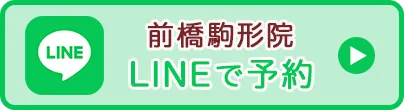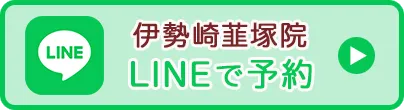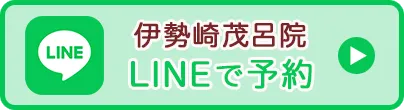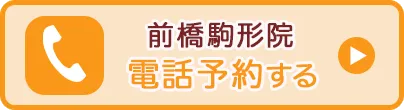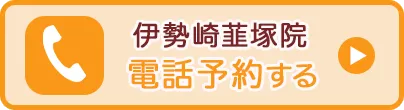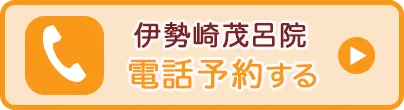めまい もくじ
・ めまいがおこったらすること ・ めまいとは? ・ めまいの種類 ・ めまいの原因 ・ 家でできるめまい予防法 ・ めまいQ&A ・ めまいの施術法
めまいがおこったらすること
①【 安静 】
・どのようなめまいでもまずは無理せず安静にしてください。 ・立っている時は転倒しないようにゆっくり座ります。できれば寝た方がよい。 ・運転中はなるべく安全な所に停車します。②【 水分補給 】
・適量の水分を摂取してください。➂【 目や耳を休ませる 】
・部屋のあかりを暗くしてください。 ・耳から入る音をなるべくさけてください。④【 医療機関を受診 】
・安静や水分補給、目や耳を休ませてもめまいが続く場合、またおさまっても頻繁に繰り返す場合はまずはお近くのめまい対応の医療機関を受診してください。 ・受診してみて脳や耳などに異常がなかった場合はめまいに対応している接骨院や鍼灸院でも施術可能です。日本めまい平衡医学会専門医検索サイト めまいの専門病院はこちら≫≫
めまいとは?
頭の位置や身体の位置を認識している体の中のセンサーに異常が生じてしまった結果、自分もしくはまわりが実際は動いてないのに動いているかのように間違った情報を感じてしまうものです。 ・見えているものがぐるぐる回る ・自分の体がふらふら揺れる感じがする ・気が遠くなりそうな感覚がある ・焦点が合わず物が二重に見える ・吐き気がする このようなめまいの症状を感じてお悩みの方が多くおられます。めまいの症状の種類
めまいの症状の種類にはさまざまなタイプにわけられます。 ここでは、代表的なめまいの症状の種類を2つご紹介していきます。 めまいのほとんどはこの2つの症状です。①ぐるぐる回るタイプ
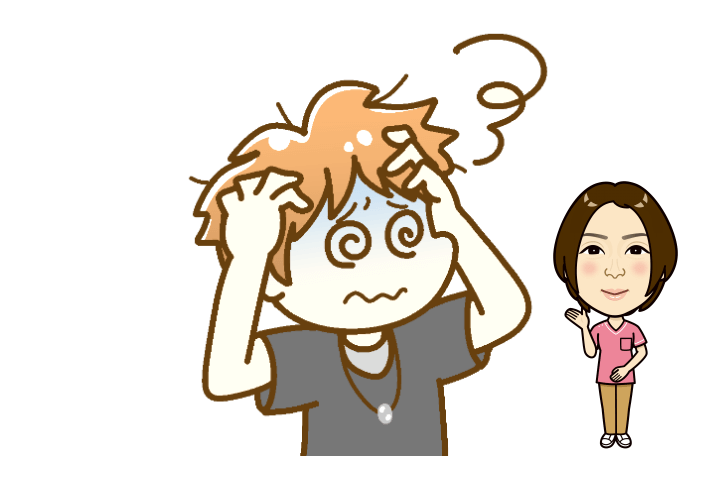
②体がふわふわするタイプ

めまいの原因
①良性発作性頭位めまい症
特徴 ・めまいの中で比較的多い ・頭を動かすとめまいがおこる ・ほとんどが1分以内と短い時間 ・50代以降の女性にとくに多い 原因 耳の奥の内耳と呼ばれる場所にある 耳石が三半規管(さんはんきかん)の中に入り込んでおこる 耳石が三半規管の中に入ることで神経が過剰に刺激されめまいがおこります。《 良性発作性頭位めまい症の詳しい説明 》
めまいの原因の多くは、良性発作性頭位めまい症といわれます。 耳の奥には内耳と呼ばれる場所があり、 内耳には三半規管と耳石器と呼ばれるものがあります。 三半規管の中には、リンパ液という液体で満たされています。 耳石器には炭酸カルシウムでできた耳石が数百個存在します。 この耳石が頭の動きによって動くと、脳に頭が動いているという情報が内耳から伝えられます。 耳石は頭部外傷や交通事故などの衝撃、中耳炎などの炎症によって剥がれ落ちてしまうことがあります。 さらに閉経後の女性はカルシウム不足になりやすいため カルシウムでできた耳石はもろくなってしまい剥がれ落ちやすくなってしまいます。 剥がれ落ちた耳石が三半規管の中に入り込んでしまうと 三半規管の中にあるリンパ液の流れが変わってしまいます。 それにより 脳に頭を動かしていないのに動かしているという情報が内耳から伝えられます。 その結果、実際の動きと脳に伝えられた情報が合わないため、めまいを生じます。 これが良性発作性頭位めまい症の仕組みです。 めまいの種類は回転性めまい、浮動性めまいが特徴的です。
②メニエール病
特徴 ・めまいと耳鳴り ・耳が詰まるような閉塞感 ・聞こえづらくなる ・長い場合は1日続くことも ・20~50代に多い ・反復しておこる 原因 内耳の平衡感覚に関与する三半規管の中のリンパ液の量が増え、リンパ液の入っている袋がやぶけてしまい感覚細胞が過度に刺激されめまいがおこります。破れた部分はいずれつながりますがリンパ液の量が増えすぎるとまた破れて再発します。《メニエール病の詳しい説明》
メニエール病によるめまいの原因は、 内リンパ水腫によるものです。 内耳の中は膜迷路という膜でわけられた二重のトンネル構造をしています。 膜の内側を内リンパ液、外側を外リンパ液と呼び、 内リンパ液が増えすぎたものを内リンパ水腫といいます。 内リンパ水腫の原因は 塩分・水分の過剰摂取、感染症による循環障害、ストレスなどといわれています。 内リンパ水腫になりリンパが貯まる袋が腫れてしまい内側と外側をわけていた膜を破ってしまうと、 内リンパ液と外リンパ液が混ざりあいます。 その結果、リンパ液の流れが乱され、バランスを保つ器官が影響を受け、めまいを生じます。 これがメニエール病によるめまいの原因です。 めまいの種類は回転性めまいで長時間続くのが特徴的です。➂前庭神経炎
特徴 ・激しいめまいが数日続くことも ・かぜの後におこりやすい ・耳鳴りや難聴は伴わない 原因 内耳と脳を結ぶ前庭神経に炎症がおこるものです。 前庭神経は三半規管などが感じた情報を脳に伝えます。 片方の耳に前庭神経炎がおこると左右違う情報が脳に伝達されてしまいめまいをおこします。ウイルス感染が原因でおこることもあります。④化膿性内耳炎
特徴 ・激しい回転性めまい ・気持ち悪さ、嘔吐 ・耳鳴り ・難聴 ・発熱がおこることも 原因 内耳に炎症がおこり発症します。 中耳炎が長引き内耳にまで炎症が起こって発生する場合や耳の周りの骨の骨折をしたときに起こる場合があります。➄脳からの症状によるもの
特徴 ・浮動性のめまい ・ふらつき ・ふわふわと浮いている感じ ・体への麻痺 原因 脳梗塞、脳出血、脳腫瘍など 脳に何らかの異常が起こり発症します。⑥首こりからくるもの
特徴 ・ふわ~っと浮いているような感覚 ・ストレートネックの方に多い ・意識が遠くなる感覚 ・貧血みたいな症状 ・立ちくらみをすることも ・耳鼻科の診断では異常なし 原因 首のずれや首のこりにより脳にいく血液や酸素の量がすくなくなっておこります。家でできるめまい予防法
①長時間同じ姿勢で座らない
テレビなどを見ているとついつい同じ姿勢でいることが多くなってしまうと思いますが、定期的に姿勢を変えて体を動かしましょう。②横向きで寝るのを続けない
同じ向きで長時間横向きで寝ていると、耳石が三半規管にたまりやすくなります。 横向きで寝ることが多い方は、定期的に反対向きで寝るようにしましょう。③生活習慣をよくする
・バランスのよい食事 偏った食事を続けていると鉄分などの栄養が足らず、めまいの原因にもなります。 ・禁煙、禁酒 たばこやお酒は体の循環を悪くしてしまいます。 めまいの原因になってしまう可能性があります。 過剰摂取には気をつけましょう。 ・適度な運動 心因性からくるめまいの予防にストレスをため込まないことは重要です。 適度な運動をして体も心もリフレッシュしましょう。④枕を高くして寝る
めまいがおこりそうな時は 頭の位置を高くして寝ると三半規管に耳石が入りにくくなります。 タオルなどを下に入れて枕を高くして寝ましょう。 それ以外はマクラは低めにして寝た方が身体のバランスにはよいです。
<めまいの改善体操>
ここでめまいが起きてしまったときに効く体操を2つご紹介していきます。 めまいの改善体操は、三半規管のなかを浮遊している耳石をもとの位置に戻すことを目的としています。 体操はすべて右耳の耳石をもとの位置に戻す方法をご紹介しますので、 左耳の場合は、左右反対の動作を行ってください。 *めまいが強い場合や体操の途中に気分が悪くなってしまった場合は、無理に動かず安静にしてください①Epley法
step1 ・真っすぐ座り、首を右に45度まわします step2 ・肩甲骨の下にタオルを入れ、仰向けに寝ます ・首を右に45度まわし、あごを少し上げます step3 ・首を左に45度まわし、あごを少し上げます step4 ・体を左向きにして、首は左に45度まわします step5 ・体を起こし、座った状態で真っすぐ前をみます 各step、5分またはめまいが消失するまで姿勢を保持します ここまでを1セットとし、めまいがなくなるまで2~3セットほど行います。②Lempert法
step1 ・仰向けに寝て、首を右に90度まわします step2 ・肘をついて、うつ伏せになります step3 ・左向きで横になります step4 ・仰向けになります 各step、5分またはめまいが消失するまで姿勢を保持します ここまでを1セットとし、めまいがなくなるまで2~3セットほど行います。めまいのQ&A
めまいが起こってしまったらどうすればいいですか?
無理に動こうとせずに、楽な体勢で休憩してください。 頭を少しずつ動かし、めまいが楽になる位置を見つけましょう。 横になれる場所があれば横になって、なるべく静かな部屋で目を閉じて安静にします。 めまいが落ち着いて動き出すときは、ゆっくりと動き出すことを意識してください。 急に起き上がったり、立ち上がったりすると再びめまいが起こる可能性があります。 頭を大きく動かすようなことも気をつけましょう。