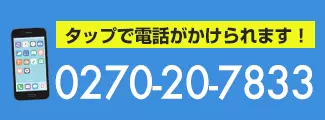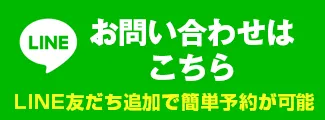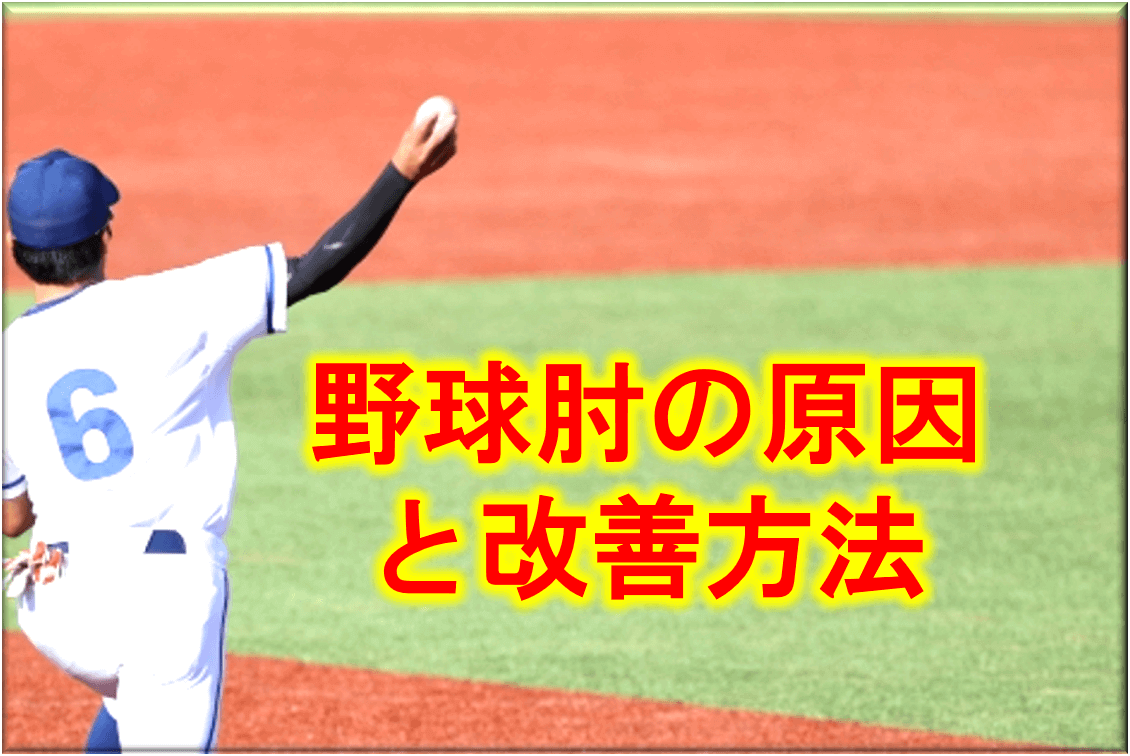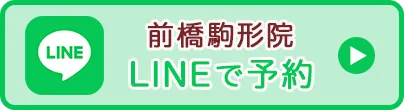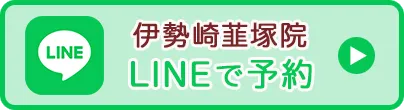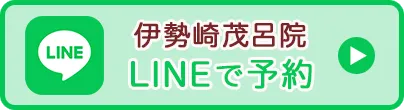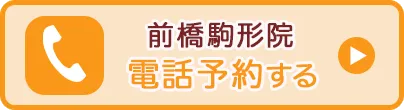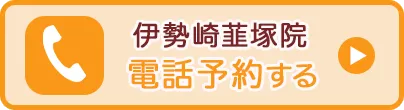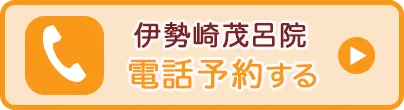野球肘 もくじ
・ 野球肘とは? ・ 野球肘の種類 ・ 野球肘の注意点 ・ 野球肘の予防法 ・ 野球肘Q&A
野球肘とは
主に投球動作の繰り返し(オーバーユース)によっておこる肘のケガの総称です。 特に成長期の子供は(小・中学生)骨や軟骨が発達途中で損傷を受けやすく注意が必要です。 肘の軟骨は単体で損傷した場合痛みを感じにくい場所として有名で、小・中学生の場合は特に肘の痛みがなくても2~3か月に一回はエコー検査を受けることをおすすめします!野球肘の種類
肘の痛む部位は肘の内側、外側、後側の3つに大きく分けられます。肘の内側の場合
小中学生では肘の内側の骨がまだ弱いため靭帯に引っ張られかけてしまうことがあります。肘を曲げて指の先が肩につかない場合は剥離骨折の疑いがあります。 学年が上がって高校生に近くなってくると骨はしっかりしてかけることはなくなります。そのかわりに肘の内側の靭帯を損傷することが多くなります。肘の外側の場合
外側の肘の痛みは上腕骨小頭離断性骨軟骨炎といい、一番早期に発見しなければならない野球肘です。 投球時に肘の骨同士がぶつかり軟骨がかけることにより起こります。 利き手と違う方の手の肘におこることもあり、成長期での血流障害や遺伝的要素も関係するともいわれています。 痛みを感じなくても症状が進んでしまっていることも多く、肘が伸びにくいなどの症状がみられたら早急に検査をする必要があります。肘の後側の場合
小・中学生では肘の骨には骨が成長するための骨端線という柔らかい部分があります。 ボールを投げるために肘を伸ばした時に肘の骨端線に離れる力が加わります。 このことで骨端線がくっつくのが遅くなったり、ひどくなると骨折のように固定をして安静にしなければ治らなくなります。 高校生になると骨端線は硬い骨になっているためこの状態を繰り返しおこると高校生では疲労骨折になることもあります。野球肘の注意点
最も野球肘になりやすい年代 野球肘は小学5・6年生が最も起こりやすい年齢です。この年代では痛みがなかったとしても特に念入りにケアをしてください。 キャッチャーの投球数にも注意 ・ピッチャーとキャッチャーが圧倒時に野球肘になりやすい。ピッチャーはもちろんキャッチャーの投球数もカウントしながら試合に臨むとよいかと思います。 ・練習日数の目安 小学生は週3回以内、一日2時間を超えないように 中学生以降は週に一日は休みを設ける ・全力投球数 小学生は1日50球まで週に200球まで 中学生は1日70球まで週に350球まで 高校生は1日100球まで週に500球まで どの年代もボールを使わないシーズンオフを設けることが望ましいといわれています。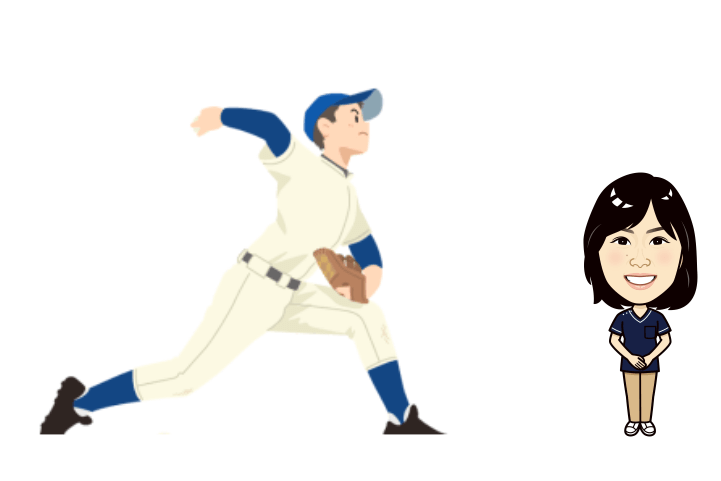
野球肘の予防法
定期にメディカルチェックをしてあなたに合った予防法をしていくとよいです。 また野球肘を予防したり早期に治すためのリハビリをしていくことも大切です! 一般的な予防法としては ・股関節や体幹、肩甲骨などの柔軟性を高めるストレッチ ・投球後に炎症が続くと組織は硬くなるので、投球後は接骨院や整形外科などで炎症を早くとることで予防できます。 ・投球動作をチェックし改善する(足の踏み込む位置や投げる際の左右の肩の高さの違い、腕の位置を下げない などを自然と行えるようにしていきます。<野球肘の予防体操>
ここで野球肘の予防、改善になる体操を2つご紹介していきます。 家でも簡単にできるので、ぜひ実践してみてください。 *痛みのない範囲で行ってください①前腕回内外運動
・テーブルに片手を置きます ・肘を固定し手の平を返します ・元に戻します これを10回繰り返し、3セット行います。 ポイントは テーブルから肘が離れないようにすることです。②前腕外側軟部組織リリース
・前腕外側を反対側の手でつまみます ・つまみながら腕を内側にまわします ・腕を元の位置に戻します これを10秒間繰り返し、10セット行います。野球肘Q&A
メディカルチェックで異常が見つかった場合はその後の流れはどのようになりますか?
メディカルチェックでは担当の臨床検査技師が検査をしていますので、エコー画像をお渡しし整形外科に接骨院から直にご紹介状を書くことができます。 定期的に整形外科に通院しながらそれ以外は接骨院で施術を受けることも可能です。 下記のページに接骨院の詳しい施術内容が書いてありますので、ぜひ参考にしてみてください。